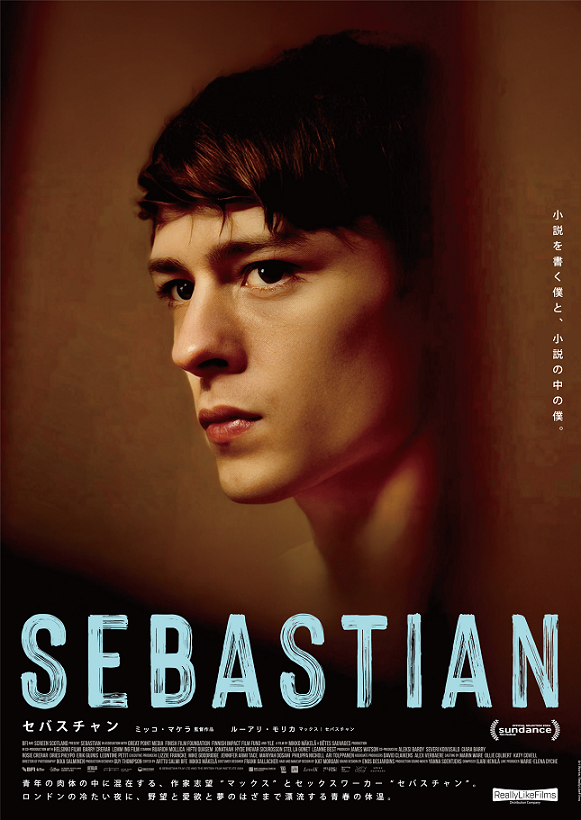隣人映画で境界を意識する
『関心領域』は、隣人映画だ。そういう映画ジャンルがあるとすれば。
迷惑をかける隣人映画なら、ザック・エフロン、セス・ローゲン主演の『ネイバーズ』、優しい隣人なら『シリアにて』。北欧映画の『隣の影』は、隣人との争いが悪意の応酬になる。『関心領域』は収容所が隣人という、特殊さで際立っている。

『関心領域』で描かれる家族には、4人の子供と、素晴らしい家と庭、お手伝いや下働きの人もいる、理想的な生活だ。父(クリスティアン・フリーデル)は、キャリアを順調に伸ばし、母(ザンドラ・ヒュラー)は、庭の手入れに忙しい。周囲には自然の美しさが溢れていて、休日に屋外でゆったりと過ごすのも贅沢だ。
道を隔てたお隣さんは、収容所。毎日処刑も行われているようだ。だが、夫婦はそれを問題だと思っていない。ごく自然な存在であり、なくてはならないもの。なぜなら父のルドルフは、そのアウシュビッツ収容所の所長なのだ。豪華な生活も、それがあってこそ。
ある日、ルドルフに栄転の話が来る。理想的な暮らしに完全に満足していた妻は、異議を唱える。「私は絶対にここを離れない」と。

物騒さや、不穏さは、日常の陰に隠れているが、確実に周囲に漂っている。普通の暮らしに見えて、普通ではない。同時に、普通でないようでいて普通。その曖昧な境界をジョナサン・グレイザー監督は、剃刀の上を歩くような、絶妙なバランスで描いている。
方法としては、決して人物に近寄らないカメラ。広いはずの家なのに、人物は、スクリーンの端に寄せて見せる。だから登場人物は、ゆったりしているようには、見えない。家の外観からは想像できないように、廊下は狭苦しい。

どのように見えるかを計算し、中立的な立場を崩さない。存在感を増していくのは、音と音楽、空気感。あくまでフラットな味わいなのに、見ている側の身体に重たい塊を、積もらせていく。ときおり挟まれるモノクロシーンは、そのダメ押しだ。
自分の物差しでしか他の世界を見ることができない私たちに、隣人映画は、改めて自分の世界と、他者との境界を突き付けてくる。その境界と、どうつきあうのか。自分の境界はどこにあるのか。それを意識することは、自分の感性の幅を広くする方法でもある。

ところで、『関心領域』は、イギリスの作家、マーティン・エイミスの著書が原作だ。原作本では、主人公家族は架空の存在に変えていた、そのモデルが、ルドルフ・ヘスファミリー。映画では、モデルだった実在の人物を主役にして、2年間にわたる綿密な取材で作り上げている。
架空から実在の存在に変えたことで、作品と鑑賞者の間にあるクッションが消え、歴史と現在との地続き具合が強まっている気がする。ちなみに『関心領域(The Zone of Interest)』という言葉は、実際にナチスが、そのエリアを呼んでいた名称だ。
関心領域
5月24日(金)より新宿ピカデリー、TOHOシネマズシャンテほか全国公開
配給:ハピネットファントム・スタジオ
©Two Wolves Films Limited, Extreme Emotions BIS Limited, Soft Money LLC and Channel Four Television Corporation 2023. All Rights Reserved.
監督・脚本:ジョナサン・グレイザー
原作:マーティン・エイミス
撮影監督:ウカシュ・ジャル音楽:ミカ・レヴィ
出演:クリスティアン・フリーデル、ザンドラ・ヒュラー
原題:The Zone of Interest|2023年|アメリカ・イギリス・ポーランド映画|公式HP:https://happinet-phantom.com/thezoneofinterest/公式X:@ZOI_movie