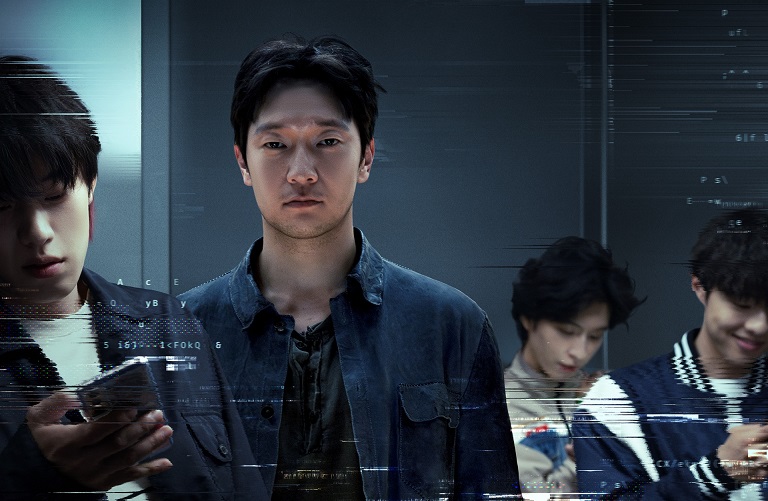時というものは残酷だ。前作からわずか数年にも関わらず、ボーゲル夫妻は明らかに老いた。外出の際は車椅子が必須アイテムとなったハーブの口数がめっきり減ったことでも、それは顕著だ。ドロシーは「私の仕事は彼の面倒を見ること」と苦笑する。
少なくとも前作の夫妻には、“世界最大の現代美術の個人蒐集家”として、新人作家を発見する貪欲さや、アトリエめぐりの愉しさがあふれていた。小さなギャラリーを隈なく覗き、創作中の作家たちと談笑する夫唱婦随のささやかでありながら、かけがえのない幸福。しかし、そんな名伯楽さながらの彼らにも、老いは確実に忍び寄る。

その一方で、ニューヨークの夫妻のアパートの一室で永遠に陽の目をみることはなかったかもしれない“埋もれた傑作”が世に問われることは、作家の再評価に繋がることは間違いない。長年、スランプに苦しむ画家は言う。「彼らに認められたから、人生は失敗じゃないと思える」。そうやって夫妻に物心ともども支えられた現代美術家は枚挙に暇ないだろう。だからこそ、このプロジェクトに一度は反対し、親交を断った作家も、やがて彼らと和解する。いや、和解せざるを得ない。無名時代の彼らの作家活動を“親のような愛情”で見守ると同時に鼓舞したのは、他の誰でもないボーゲル夫妻だからだ。たとえコレクションが彼らの許から離れても、“発掘”された感謝の念は親と子の絆のように永遠だ。

こうして、夫妻のコレクションの時は幕を閉じた。愛猫と独り残された部屋でパソコンに向かい、各美術館のホームページに目を光らせるドロシーの気丈な未来に、私は幸あれかしと祈るばかりだ。(増田 統)
ハーブ&ドロシー ふたりからの贈り物
3月30日(土)より、新宿ピカデリー、東京都写真美術館ほか全国順次ロードショー