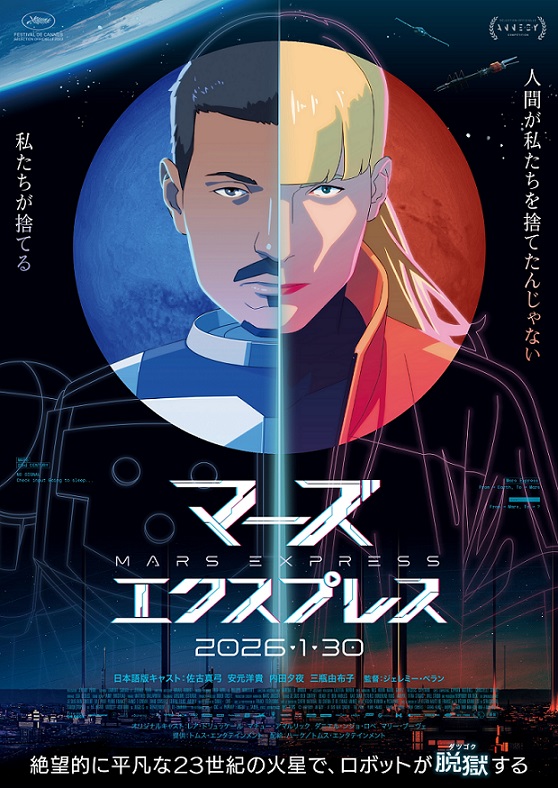わかりきったことで口幅ったいが、生と死は裏合わせである。生を語ることは死を語ることであり、死を掘り下げることは生を掘り下げることである。この映画の主人公・佐伯(大杉漣)は教誨師として6人の死刑囚と向き合い、対話する。そうする中で彼自身もみずからの生と死を見つめざるを得なくなる。やがて浮きあがるもの、それは誰もがやがて確実に死を迎えるということだ。
わかりきったことで口幅ったいが、生と死は裏合わせである。生を語ることは死を語ることであり、死を掘り下げることは生を掘り下げることである。この映画の主人公・佐伯(大杉漣)は教誨師として6人の死刑囚と向き合い、対話する。そうする中で彼自身もみずからの生と死を見つめざるを得なくなる。やがて浮きあがるもの、それは誰もがやがて確実に死を迎えるということだ。
非常に生真面目なテーマだが、演技陣はきらびやかで、対話のひとつひとつはどことなく滑稽味を帯びる。教誨師は偉そうなことを言うわけではない。やくざの組長(光石研)は陽気で親しみやすい。ひたすら沈黙を守る男(古舘寛治)は興味をそそる。関西弁でしゃべりちらす女(烏丸せつこ)には背筋がひんやりする。わくわくさせる顔を持つ俳優たちが、次々に佐伯と対話するが、ひとつの対話は長くならず、映像はリズミカルで凝縮されている。
中に「問題児」が一人いる。大量殺人を犯したことを正当化する若者(玉置玲央)で、佐伯にからむように独自の理屈を言い立てる。佐伯は挑発に耐えながらみずからの過去の記憶=傷を語るが、それも若者の屁理屈の餌食になるばかりだ。「問題児」は自分の最も深いところを刺してくる、そう考えた(であろう)佐伯は苦しんだ末にひとつの境地に至る。それは「(若者の)空いてしまった穴を見つめる」、「自分はそばにいる」決意を彼に明確に示すことだ。
脚本・監督の佐向大は、かつて『休暇』(門井肇監督)という映画の脚本を手がけている。吉村昭原作による、ある死刑囚(西島秀俊)と実直な刑務官(小林薫)の交流を描いた佳作である。刑務官の最も重い役目は刑を執行された者の身体を受け止めることだ。そのことと、刑務官が再婚相手の幼子を抱き上げるシーンが重なる。死を受け止めることと生を抱き上げることには同じ覚悟が必要であり、それは愛とよばれるものから生まれるのである。
さんざん悪態をついた若者が、刑の執行を前にして佐伯に抱きつく。このシーンの心は『休暇』で描かれたものと同じである。そこにあるのは、死刑囚とそうでない者との境目を作らずに人間の生死を見つめる心である。そのことをどこまで誠実にまっすぐに描けるか、本作もまた果敢な挑戦の映画になった。
ありふれた物言いだが、大杉漣はまるで遺言のような作品を残して去った。女性の車に乗って帰途についた佐伯が、ふと気づくとひとりぼっちになっているシーンは幻影だろうか。その幻影は生きている者のものなのか、亡き者のものなのか判然としないが、おそらく後者ではないだろうか。口惜しいけれど、そういう風に考えることで、大杉漣が見事に「完成」したと信じたいのである。続編の予定があったと佐向大監督は言う。続編がなくてもいい。ありがとう。
(内海陽子)
教誨師(きょうかいし)
(c)「教誨師」members
10月6日(土)より、有楽町スバル座、池袋シネマ・ロサ他にて全国順次公開
監督: 佐向大
出演: 大杉漣 (佐伯保)
玉置玲央 (高宮真司)
烏丸せつこ (野口今日子)
五頭岳夫 (進藤正一)
小川登 (小川一)
古舘寛治 (鈴木貴裕)
光石研 (吉田睦夫)
2018年/日本/カラー/ 114分/スタンダード(一部、ヴィスタ)/ステレオ
配給:マーメイドフィルム、コピアポア・フィルム 宣伝: VALERIA、マーメイドフィルム