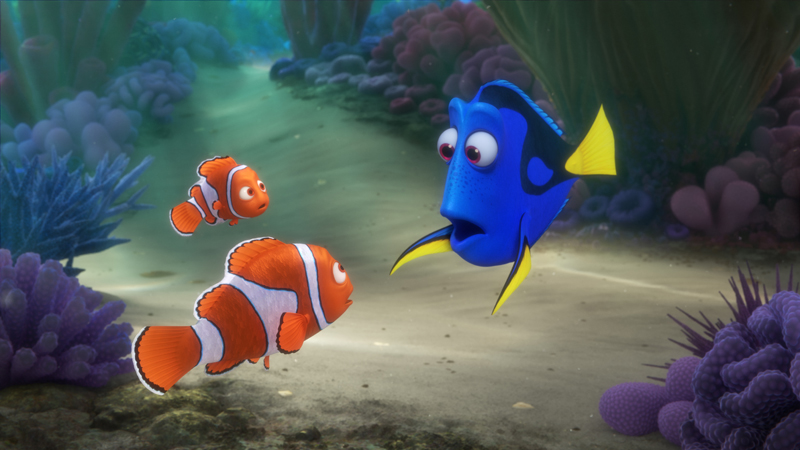9月17日より、映画『オーバー・フェンス』が公開となりました。本作について、内海陽子、オライカート昌子が対談を行いました。
映画『オーバー・フェンス』とは
映画『オーバー・フェンス』は、生涯で5度芥川賞にノミネートされながら受賞を果たせずこの世を去った佐藤泰志原作の三度目の映画化。函館を舞台に、純粋で不器用な者たちの一瞬一瞬の姿を鮮やかに描き出したのは、山下敦弘監督。オダギリ・ジョーと蒼井優が、今まだにない新鮮な演技でスクリーンを彩る
内海:わたしは山下敦弘監督が前々から好きで、一番好きなのは『天然コケッコー』(2007)という親と子の屈折した青春を描いた作品です。これはどなたにでもおすすめです。他にも話題作の『苦役列車』(2012)や『マイ・バック・ページ』(2011)などを監督しています。
元々はインディペンデント系の監督ですが、腕を買われて今は職人監督としても活躍しています。今年は松田龍平主演『ぼくのおじさん』も公開されますね。今回の作品、『オーバー・フェンス』は、初心に帰ってひとつの素材を自由に撮らせてもらえたのではないかなと思って、今のところ、彼の作品の中で一番好きになりました。
原作は佐藤泰志という函館出身の不遇な作家です。佐藤泰志原作の三度目の映画化が『オーバー・フェンス』となります。映画化された前二作は、『海炭市叙景』(2010)と『そこのみにて光輝く』(2013)という作品で、二作ともわたしはちょっと苦手でした。乱暴な言い方をすれば、ネクラな日本映画、と映画にあまり興味のない人に言われかねない作品だったと思います。

『オーバー・フェンス』は、同じ作家の作品をバトンタッチされるような感じで山下監督が引き受けたわけですけれど、素晴らしい出来です。原作の作品世界に縛られていないというか、作品との対峙の仕方が伸びやかというか自由というか。つまり向き合う自分に自信があるのかなあとも感じました。職業訓練校の中の群像劇は、崔洋一監督の『刑務所の中』(2002)を思い出しました。
オライカート:刑務所の中にしか見えないですね。
内海:それがなんとなくおかしくて。みんな深刻なのに、どこかピントがずれていてオフビートな雰囲気ですね。深刻さの輪郭が淡いというか。それがとても気持ちいいなあと。
監督の原作に対する立ち向かい方に感動した
オライカート:オダギリ・ジョーと蒼井優が主演の二人を演じていますが、オダギリ・ジョーは蒼井優の演技を引き立てるように受けの演技に徹しているところが素晴らしかったです。またさとしを演じる蒼井優は自由に羽ばたく演技が見事でした。
さとしによる鳥の求愛ダンスが映画の中の重要な要素として出てきます。これは原作にはないそうで、映画オリジナルですが、二人の出会いのきっかけでも、ヒロインのさとしを印象付けるという意味でも象徴的に描かれています。わたしは原作は知らないのですが、お読みになられましたか?
内海:映画を見て原作が読みたくなるタイプのものと、そうではないタイプのものがありますが、『オーバー・フェンス』に関しては後者ですね。映画は面白いと思ったのですが、だからと言って原作を読みたくなる映画ではないんです。
監督の原作に対する立ち向かい方に感動したというか。原作者と監督の対話の仕方に魅せられた。映画の醸し出す空気、人間がぶつかったり、悲しんだりいろいろなことがあるんだけど、そのこすれあいというか、それが素敵だなと思いました。やっぱり余裕があるんですよ。人間がいろいろなふれあいをするんだけど、こちらにあまりきついものを向けてこない。
オライカート:さとし(蒼井優)は壊れているけれどその理由は描かれていない。白岩(オダギリ・ジョー)に関しては描かれています。とても打撃を受けることだけれど、さらっと描かれているだけでなく、それは過去のことだからと焦点を当てていない。

その喜びの瞬間というものが、日常というものにヒビを開け滲み出る。そういうことが描かれているのが特徴的だと思いました。その瞬間瞬間的な喜びと言うものがタイトルの『オーバー・フェンス』というものとラストシーンで特に象徴的に描かれています。少し文学的でもある。
内海:この映画は文学の映画化ですが、わたしは、この映画は文学的でない部分がとてもいいと思う。文学的というよりは肉体的な感じ。肉体的というのは瞬間瞬間と言うあなたの言っていることと同じです。文学と言うことを意識すると少し観念的になってしまう。理屈つけようとしたり、意味を持たせようとしたり。この監督はそれを嫌っているんですね。そういう形で文学と対峙しようとする山下監督はとてもチャーミングです。
オライカート:肉体の感覚は、こちらにも伝わってきます。一つ一つのキーワードごとに。たとえばさとしの行水の場面など。
内海:あのシーンは厳しいですよね。ごしごしと身体を拭く。自虐行為ですよね。
オライカート:あそこは、白岩が少しずつ変化していくきっかけにもなりますね。
蒼井優という女優は玉虫色の引き出しを持っている
内海:わたしは、蒼井優は日本の若手の女優の中でナンバーワンじゃないかと思っています。今までで一番素晴らしかったのはタナダユキ監督の『百万円と苦虫女』(2008)。ちょっとしたことで刑務所に入ってしまった娘が、出所後、自立するために、なんとかして百万円貯めるんだと決意して旅をする物語です。
『オーバー・フェンス』で山下監督は、彼女の今までの演じ方を一回チャラにして、全く違うものを求めたんじゃないかと思います。そのことで彼女はとても苦しんだというのは、まず発声に出ていますね。
あんなに苦しそうな、喉を痛めるような発声をするんですね。私は彼女を好きだから声もよく知っています。アルトの落ち着いたきれいな声をしている人なのに、この映画ではヒステリーのような発声なので、心配でした。見ているわたしも嫌いになるんじゃないかと思ったのですが、全然そうならなくて、蒼井優という女優が玉虫色の引き出しを持っているのではないかと、わあすごいな、またひとつキャリアを積んでいるな、そこに立ち会っているような喜びを感じました。
映画に出演するというのは映画の中で生きることだと思いますが、彼女はその表現がぴったりの女優さんだと思います。
オライカート:そういう意味で彼女の映画をもっと見たいなと思わせる女優さんですね。
内海:今回、発声の仕方で声をつぶすんじゃないかと不安でしたが、ああいう形で、精神不安定な、生き方がへたくそな、自分をいつもいつも追い詰めてしまう、それでいてフラッパー的なところもあるという、そういう人をちゃんと存在させています。

内海:なんでそうなったかとか、そういう問題ではない。その人の中に入ってみれば、誰でもみんな不安なわけ。それをどこかで折り合いをつけ、大人になればもう大人なんだからとか、自分で納得させて、ある種紋切り型で生きるのよ。現実ってそういうものじゃない?
蒼井優が演じているさとしは、それができない人なのよ。いつもまっさらでそのときの欲望に正直で。だから傷つく度合いも激しいし、で、傷ついたから、そこから学ぼうとか、そういうセコイことも考えずに、いつもいつもどんどんどんどん突き進んじゃうのね。
それで水商売に入ってるから、すぐにやらせてくれる女だとかレッテルも貼られてしまう。それでも怒ったりしない。というのもたくさん傷ついてしまっているから。その彼女にオダギリ・ジョー演じる白岩は、最初の求愛のダンスを見て、求愛の叫び声を聞いて、ピンとくるんでしょうね。頭では理解できないけれども。
そういう恋の始まりってあるんだなあ、と思って。理屈ではなく、なんかピンとくる恋の始まり。いろいろな傷があるから、幸せなポッと頬を赤らめるというような恋の展開にはならないけれども、でもあるんだよね。
それは、まぎれもない恋の始まり
厳しい喧嘩のシーンもあるけれど、そこでようやく男の方が自分を全開せざるを得ない。それまでは少しかっこつけて、ニヒルをきどっていたけれど。彼女に剥き出しで迫られると、つい本音が出てしまって、かっこつけていた鎧が剥ぎ取られる。そこからスタートするわけよね。
男と女に限らず、本音の付き合いと言うか、その人が見えた、その人に触れることが出来た瞬間というのはきっとああいうときのことなんでしょうね。抱き合うとかキスをすることではなく、その人の何かにピッと触れて、もちろん傷つけてしまう、自分も傷つけられてしまう、それでももうちょっと先に行ってみようとか、そういうことなんでしょうね。
オライカート:恋愛と言うように単純化して描かれていなくて、人対人としての、友情も含めた人間と出会ったという、それをすごく感じましたね。

ラストシーンは、もし肩透かしだったら、失望させたら許さないぞ、と久々に本当に心の底から思いました。白岩にホームランを打ってほしいなと。なんか単純な話なんだけどさ、泣けちゃいましたよ。うれしくて。
オライカート:『オーバー・フェンス』というタイトルにはいろいろな意味があるとは思うのですが、とても鮮やかなラストでした。
この映画には二種類の人々が描かれていると思いました。人生に打ちひしがれているように見えるさとしと白岩は、一瞬の喜びの瞬間を待ち望むように生きている。一方松田翔太演じる代島や教習所の先生は、人を操作しようとし、自分の考えに支配されている。今の社会でいうと、まあ勝ち組のようなイメージですね。
内海:勝ち組や負け組みというのは、ちょっと単純化し過ぎよ。あの先生は勝ち組ではないですよ。ストレスを抱えているから人をいじめるわけだから。
オライカート:勝ち組というのは言い過ぎかもしれないですが、松田翔太演じる代島は、さとしのことも一定の見方しかしない。
一瞬一瞬の喜びの描き方の比重が映画を決めている
内海:勝ち組負け組という言葉はマスコミが作ったもので、世界はそのように単純なものではない、というのがこの映画だと思います。あなたがそういう風に考えるなら、そういう考え方を軌道修正しないと、この映画の神髄に触れることはできないですよ。『葛城事件』でも描かれていましたが、人は単色ではないのだから。ふきこまれた情報によって何かを決め付けるのは恥ずかしいことだと思っています。
オライカート:先ほどの言葉を補足して一番言いたかったのは、代島や教習所の先生は、自分の思考に支配され、生きている。一方、打ちひしがれて生きているように見える白岩やさとしの方は、その中で、一瞬一瞬の喜びを待ちわびている。そこを描いているということなんです。そして一瞬一瞬の喜びの描き方の比重が映画を決めている。
内海:言葉の使い方は違うけれど、わたしたちは同じことを言いたいのではないかと、今思いました。さとしと白岩は、強くて自由なのよ。平気で打ちひしがれるという意味で。

内海:二人は、ある意味で傲慢なのかもしれませんね。そして嘘をつくことを頑として拒否しているというか、何か言ったら嘘になるから、何も言わないことを選んだのが白岩。さとしの場合は踊っちゃう。説明したり、誰かに言い訳をするんだったら、求愛のダンスをする。好きな男にはぶつかっていく。
そういう人は現実の世界ではなかなか見ないから、映画ならではの登場人物ですよね。周りはまるでギャラリーのよう。二人を取り巻いてざわめいている群衆みたいですね。何か特別な能力のある人だけが、二人のような剥き出しの生き方が出来るんじゃないかと思わせます。とても高邁な感じもしますし、同時にとても慕わしい。みんなが本当はこういう風になりたいなということを、二人が代弁してくれているのかもしれませんね。
オーバー・フェンス
2016年9月17日(土)テアトル新宿ほか全国ロードショー